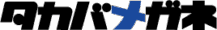はじめてのめがね、かわいい?
はじめてのめがね
子供に良いめがねをかけてもらいたい。
入園前の小さい子供さんや保育園・幼稚園などへ通園されている園児をお持ちの御両親は、子供がメガネをしなければいけなくなった時、よくこんな風にいわれます。『こんなに小さいうちからメガネをかけて将来どうなるんだろう。』
御両親の心配はごもっともですが、ある意味では子供さんの眼の屈折異常に気付いてあげて大変良かったと思います。 御家庭での様子から気付く場合や子供さんの眼の位置を見て気付く場合、3歳児検診を受けてわかる場合いろいろあります。
大事なのは、気付いた時点ですぐにお近くの眼科で診てもらうことです。というのは強い遠視、近視、乱視などがある場合、ピントの合った像を見ていないということになります。このまま矯正しない状態で放っておくと、小さい子供さんの眼(視力)の発育に悪い影響を及ぼします。

こどもさんの眼の位置をよく見てください
調節性内斜視
眼の位置をみて気付いてください
さてここで『眼の位置を見て気付く場合というのは、どういうこと?』とお思いになる方が多いと思いますので、小さい子供さんに多い遠視と内斜視について説明します。
皆様が近くを見る時に、眼の中でどういう仕事をしているかと申しますと、まず近くのものを見ようとして両眼![]() を目標物の方向(内側)に向けます。また同時に目標物にピントを合わせる為に水晶体(眼の中のレンズ)を厚くします。このように2つの仕事を同時に行っています。 眼を内側に寄せる運動を輻輳(ふくそう)と言い、また水晶体によるピント合わせの運動を調節と言います。ここで大事なのは、調節と輻輳が同時に行われていることです。
を目標物の方向(内側)に向けます。また同時に目標物にピントを合わせる為に水晶体(眼の中のレンズ)を厚くします。このように2つの仕事を同時に行っています。 眼を内側に寄せる運動を輻輳(ふくそう)と言い、また水晶体によるピント合わせの運動を調節と言います。ここで大事なのは、調節と輻輳が同時に行われていることです。
遠視のお子様の場合を考えてみます。遠視の場合は、遠くを見ている時も調節してものを見ています。ということは、先ほど説明しました輻輳も行っていることになります。遠視の度数が弱い場合は、眼位も正常ですが、強度の遠視では、調節に伴う輻輳刺激が強くなり眼が内側に寄ってしまい内斜視が起こります。 これが調節性内斜視とよばれるものです。このように乳幼児で内斜視がある場合は、強い遠視が考えられます。すぐに眼科で診てもらってください。適切な遠視のメガネを装用すれば眼位(眼の位置)も普通(正位)に戻ります。
良いこどもようめがねとは?
1 光学性能の良いレンズを使い、正しいレンズ度数、正しい瞳孔間距離、 正しいフィッテングを施したもの。
2 子供の激しい動きに対しても機能性を失わず壊れにくいもの。
3 万一破損した場合でもパーツの供給等アフターが万全であるもの。
4 色、形などデザインを楽しめるもの。
5 価格が手頃である。

みえるかな?
視力の発育について
平均的な視力の発育
| 生後1~2ヶ月前後 | 眼前20cmところで手を振ったのが分かる程度の視力 |
| 生後6ヶ月前後視力 | 視力 0.04〜0.08 |
| 生後9ヶ月前後視力 | 視力 0.1〜0.15 |
| 生後19ヶ月前後 | 視力 0.3〜0.4 |
| 4歳前後 | 視力 0.8 |
| 6歳前後 | 視力 1.0 |
眼鏡の保険適用について
■ どういう場合に保険適用になるの?
子どものメガネと言ってもすべてが対象になるわけではありません。9歳未満の子どもで、眼科の先生が「弱視・斜視・先天性白内障術後」等の治療のために、メガネが必要と判断した場合のみ対象になります。したがって、遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様の場合は対象になりません。
■ どこに申請するの?
あなたが加入している保険団体に申請します。(健保組合・社保・国保・共済組合など)健康保険証の表の一番下に、「保険者」として名前の表示がされていますのでご確認ください。申請に対する問い合わせや相談等は、こちら(保険者)にすることになります。
■ いくら戻ってくるの?
保険が適用された場合、購入した眼鏡代金の原則7割が戻ってきます。(義務教育就学前までは8割)なお、お住まいの自治体の乳幼児医療が適用され、医療費が無料とされる対象の年齢のお子様の場合には、残りの3割(もしくは2割)が各自治体から支給されます。受給資格証(ピンクのカード・みどりのカード)が支給される年齢です。保険が適用される眼鏡代金の上限は40,492円ですから、その7割28,344円が支給金額の上限になります。40,492円を超える眼鏡を購入された場合、差額は全額自己負担となります。(乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合に、自己負担2割とされ、8割が支給されることもあります。)
■ 年に何回支給されるの?
5歳未満の場合は1年に1回です。5歳以上で9歳未満の場合は2年に1回です。
| 作成年齢 | 療養費支給申請が可能 |
| 5歳未満 | 前回申請(作成日)から1年以上経過 |
| 5歳以上9歳未満 | 前回申請(作成日)から2年以上経過 |
注:なお、9歳以上の子供さんの場合、眼科の先生が治療用と判断されたメガネの購入代金は、医療費控除の対象となります。
保険申請の手順
保険が適用されると言っても、病院でメガネを給付されたり、購入出来るわけではありません。眼科の先生に「保険給付の対象となる治療用メガネであるかどうか」をご確認の上、ご自身で手続きを進める必要があります。
保険申請の際には、必要とされる以下の3点の書類を用意の上、ご加入の保険者(健保組合・社保・国保・共済組合など)に持参もしくは郵送して手続きします。
① 療養費支給申請書等
保険者が用意してくれます。保険申請の際、その場で記入することも出来ます。
② 領収書
メガネを購入した際の眼鏡店の領収書です。メガネ購入時に、一旦全額を自己負担で支払います。誰のメガネかがはっきりわかるよう、領収書の宛名はお子様の名前にし、但し書きには「治療用眼鏡代」などと書き込んであることが必要です。
③ 医師による証明書(弱視等治療用眼鏡作成指示書など)
受診された眼科から発行されます。健康保険から療養費の支給を受けるためには、眼科の先生に「このメガネが眼の治療のために必要である」ということを証明してもらう必要があります。なお、証明書の日付は、メガネの領収書の日付よりも前(もしくは同日)になっていることが条件とされています。
その他注意事項
■ 口座番号と印鑑
保険申請を行う場合には、療養費の支給が認められた場合にお金を振り込んでもらう口座番号と印鑑が必要です。ご用意お忘れなく。
■ 必要書類はコピーを
乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合、市町村役場で支給申請する際に、保険者から届いた「支給決定通知書」の他に「弱視等治療用眼鏡作成指示書」「領収書」など、各種書類のコピーの提出を求められる場合もあります。また、万一のトラブルに備え、保険者に書類を提出する際には上記①、②、③のコピーを手元に残しておくようにしましょう。
■ 乳幼児医療の申請について
治療用眼鏡として保険が適用された場合、7割(もしくは8割)が療養費として支給されますが、乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合、自己負担した残りの3割(もしくは2割)が各自治体から支給されます。詳しくはお住まいの自治体の担当課にお尋ねください。原則としては、受給資格証(ピンクのカード・みどりのカード)が支給されるお子様が対象となります。支給申請については、保険が適用され、支払通知が届いた後に、お住まいの自治体のこども課・子育て課などで行ないます。